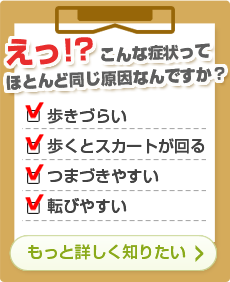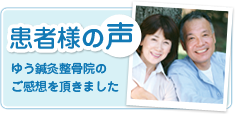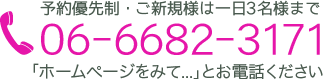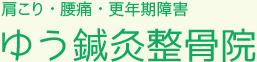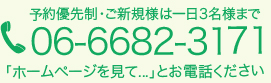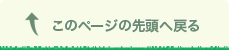新着情報
花粉症とは、花粉が体の中に入った時、免疫が花粉を敵とみなして抗体を作ります。
抗体ができた後に再び花粉が体内に入ると、ヒスタミンなどの化学伝達物質が放出され、鼻水やくしゃみなどのアレルギー症状をおこします。
花粉症の発生や症状を抑えるには、花粉の侵入経路である喉や鼻の粘膜を丈夫にしたり、身体の免疫力を高め、抗体や化学物質の発生・増加を抑えることが重要となります。
花粉症を抑える食品
・ヨーグルト
乳酸菌は、腸内環境を整え免疫力を高めることでアレルギー症状の緩和に効果があると言われています。
特に最近では乳酸菌の種類ごとの研究が進み、BB536、フェカリス菌、L-92、KW菌などでアレルギー症状への効果が報告されています。パッケージに書いてあるものもあるのでよく見てみましょう。
・レンコンやトマト、シソ
レンコンやトマトの皮、シソに含まれるポリフェノールの一種
タンニン・ナリンゲニンカルコン・ロズマリン酸などはポリフェノールの1種。
ポリフェノールには抗酸化作用があり炎症を緩和したり、アレルギーを起こす物質の増加を抑制するとされていて、その効果が報告されています。
緑茶や甜茶、べにふうき茶
緑茶などに含まれているカテキンもポリフェノールの1種。くしゃみや鼻水の原因と言われているヒスタミンの増加を抑制します。
甜茶に含まれる甜茶ポリフェノールやべにふうき茶中のメチル化カテキンは、効果が高いと言われ注目されています。
青魚
サンマやサバ、イワシなどの青魚に多く含まれる不飽和脂肪酸のEPAやDHAも、アレルギーの原因となる物質の発生を抑える働きをもっています。アトピーやぜんそくなどにも効果が報告されています。
ただし、EPAやDHAは酸化されやすいため、青魚はできるだけ新鮮なものを選んだり、ビタミンA・C・Eなどの抗酸化物質を合わせて摂るようにしましょう。
緑黄色野菜やうなぎ、レバー
ニンジンやホウレン草、かぼちゃなどの緑黄色野菜やうなぎ、レバーなどにはビタミンAが多く含まれています。
ビタミンAは粘膜を丈夫にして花粉やウイルスの侵入を防ぎます。また、風邪予防や抗酸化作用があります
上手な摂り方
上記に紹介した食品は、花粉症の症状がでる前から継続して摂り続けた方が効果が期待できます。
①毎食ごとに緑茶を飲む
②朝食や間食にヨーグルトを食べる
③ビタミンA・C・Eが豊富な野菜を食べる
④レンコンを調理して作り置きしておく
⑤青魚にシソを薬味として食べる
レンコンは皮ごと食べるのがいいそうです
調理してしまうと意外と皮も気にならないので大丈夫!
全て一気には難しいですが
少しずつ実践していきましょう!
4月も終わりに近付き、花粉の季節もあと少しで落ち着く頃になってきましたが
まだまだくしゃみ・鼻水・鼻づまりで悩まれている方が多いです
花粉を出来るだけ体内に入れないことも重要ですが
栄養バランスの崩れや、加工品・ファストフードなどに偏った食事、生活習慣の乱れは花粉症やアレルギーの症状を悪化させてしまいます。花粉症対策としてだけでなく、日々の健康づくりのためにも、ぜひ一度見直しをしてみましょう。
肉や揚げ物などの食べ過ぎに注意!

近年、低炭水化物ダイエットなどの流行もあり、ごはんなどの主食を減らして、肉などのおかずを多く食べる人が増えています。
しかし、たんぱく質や脂質の摂りすぎは、消化に負担をかけて腸内環境を悪化させたり、体の免疫が過剰反応をおこしたりする原因になります。
また、揚げ物やマーガリン、マヨネーズなどの油に多く含まれるリノール酸は、摂りすぎると炎症を促進します。食事はバランスを大事にし、油脂類は1日当たり大さじ1杯程度を目安にしましょう。
おかずも肉類ばかりに偏らず、魚など様々な種類のおかずをとりいれましょう。
お酒の飲み過ぎや喫煙は悪化の元
健康に害があることはよく耳にすると思いますが、アルコールやタバコは、喉や鼻の粘膜を刺激し、活性酸素を増やして花粉症の症状を悪化させてしまいます。
赤ワインはポリフェノールを含むため、花粉症対策で飲まれている方もいるかもしれませんが、あくまで量には注意しましょう。
外食やインスタント食品ばかりはやめましょう
食事バランスの乱れや、外食やインスタント食品、ファストフードでは身体に必要なビタミンやミネラルが不足しがちになってしまいます。
特に免疫機能を正常に維持するビタミンB6や亜鉛、
抗酸化作用を持ち炎症を抑えるビタミンA・C・Eなどは積極的に摂りいれるといいです
外食では、単品での注文はできるだけ避けて、定食スタイルやサラダセット、小鉢のセットなどを選んだり、野菜増量のメニューを選ぶのがおすすめです。
砂糖の摂りすぎに注意!
東洋医学では、砂糖の摂りすぎは身体を冷やし、血行を悪くして炎症を悪化させると考えられています。甘いお菓子やジュースなどの砂糖がたくさん入っているものは控えめにし、温かいお茶など身体を温める食品を摂りましょう。
花粉症がひどい方は一度食事の面も意識してみてもいいかもしれません
高齢者の骨折は、若年者と違っていつくかの骨折しやすい特徴があります
①【骨に脆弱性がある】
高齢者には骨粗鬆症などの基礎疾患を有している場合が多く、軽微な転倒などでも容易に骨折に至ります。
特に閉経後の女性はホルモンの関係から骨が脆弱化しやすいので注意が必要です。
②骨折の治癒が遅い
子どもの骨折とは異なり、高齢者の骨折では自家矯正力が乏しいので
一度骨折してしまうとなかなか治らず、治療が遷延し、認知症などの症状を悪化させることもあります
③骨折を起こしやすい部位がある
高齢者の骨折には4つの好発部位が存在します
それは、、、
・大腿骨頸部骨折
・上腕骨外科頸骨折
・脊椎圧迫骨折
・橈骨遠位端骨折
です
大腿骨頸部骨折
高齢者に発生する場所で頻度の高いもので容易に発生し、股関節周囲の痛みのために歩行か難しくなります
骨折部位により頸部骨折「内側骨折」と「外側骨折」に分けられます
大腿骨は股関節からすぐのところ(大腿骨頸部)で曲がっています。人間はその曲がった大腿骨で体を支えていまふが、曲がったところは転倒や転落時に外力が集中しやすく、骨折しやすいのです
この骨折は骨粗鬆症で骨が脆くなった高齢者に多発することで有名です
年間10万人が受傷し、多くの方がこの骨折をきっかけに寝たきりや閉じこもりになってしまいました
医学的には病態が大きく異なりますので
関節の中で折れる場合(大腿骨頸部内側骨折)
と関節の外で折れる場合(大腿骨頸部外側骨折)
に分けて考えます。
・内側骨折は骨粗鬆症がある場合。ちょっと脚を捻ったくらいでも発生することがあります。
よくあるのは「高齢者が何日か前から足の付け根を痛がっていたが、ある時急に立てなくなった」というエピソードです。
おそらく立てなくなった時、骨折部でズレが生じたのでしょう。
・外側骨折
内側骨折と違い、明らかな転倒・転落で発生します。
・両者の違い
内側骨折:血液循環が悪いため骨癒合が得られにくいが、関節内での骨折のため周りにスペースがなく内出血が少ない
外側骨折:骨癒合は得やすいが受傷時の外力が大きく、内出血もするため全身状態に影響出やすい
上腕骨外科頸骨折
上腕骨頭と大・小結節を結ぶ線との間の部分を外科頸といい、この部分が骨折することをいいます
上腕骨よ近位部(中枢側)に起こる骨折のなかで、この外科頸部が最も多く骨折しやすくなります。
転倒して手や肘をつくときに起こり、骨折してしまうと近くを走る大血管や神経が骨片(折れた骨の欠片)によって損傷してしまうこともあります
脊椎圧迫骨折
骨粗鬆症になると、尻もちはもちろん、くしゃみや不用意に重いものを持ち上げたりといった、ちょっとしたきっかけで椎体が潰れることがあり、いつの間にか骨折していることもあります
圧迫骨折のときは痛みを感じない人もいますが、激痛が起こる人もいます。
脊椎圧迫骨折の症状は以下の通りです。
(1)鈍い痛みが断続的に続く
(2)起き上がる・立ち上がるときに痛む
(3)長時間座っていると痛む
(4)背骨を軽く叩くと不快な感じがする
(5)脚に痛みが走る
(6)脚に力が入りにくい
(7)寝返りをうつと痛む
(8)仰向けに寝られない
脊椎圧迫骨折を長期間放置しておくと、背中ぎ丸くなる円背が起こったり、身長が縮んだりします
橈骨遠位端部骨折
手のひらをついて転んだり、自転車やバイクに乗っていて転んだりしたときに、前腕の2本の骨のうちの橈骨(とうこつ)が手首のところで折れる骨折です。特に閉経後の中年以降の女性では骨粗鬆症で骨が脆くなっているので、簡単に折れます。
若い人でも高いところから転落して手をついたときや、交通事故などで強い外力が加わると起きます。子どもでは橈骨の手首側の成長軟骨板のところで骨折が起きます。
いずれの場合も、前腕のもう1本である尺骨の先端やその手前の部分が同時に折れる場合もあります。
骨粗鬆症と診断された方は特に気をつけてください
上腕骨顆上骨折とは
上腕骨の遠位部分(体の末端側)にある上腕骨の「顆上部」の骨折
もともと骨が細くなっていることから脆弱な部分といえます
小児や子どもの中でも男女比:2:1の割合で男児に好発し
主に高所からの転落時に手を床につき、肘が反る方向(伸展)に強制された場合に受傷します
上腕骨顆上部は、すぐ近くに神経や血管が走行しているため、折れた骨の転位や腫れの程度によって合併症を招く恐れがあるため注意が必要です
症状は
上腕骨遠位端の内側上顆部と外側上顆部を結ぶ線よりもやや上の顆上部に限局性の圧痛を触れます
また同部を中心に強い腫れや皮下出血が出現します
顆上骨折には「伸展型」と「屈曲型」があり、レントゲン写真で骨折線を横から見た場合
伸展型は前下方から後上方に走行しており、屈曲型の場合は逆に前上方から後下方へ走行しています
転位のある場合伸展型の骨折では中枢骨片が前方に突出し、肘頭(肘の後端)が後方へ偏位ひた変形を生じます。
また、末梢骨片の内側転位と内旋転位(内側に軸回旋)を生ずると、前面から見て、肘関節が内反(内側に沿った形状)して見えます。
一方、屈曲型の骨折では、中枢骨片が後方へ転位し、肘頭よりも上位で後方へ出っ張った骨を触知します。
ただし、屈曲型ら転位が僅かな場合がほとんどです
尚、伸展型で大きな転位がある場合、腫脹が高度で表皮に水泡形成がみられる症例もあります。また、そのような転位のある場合、合併症としてフォルクマン拘縮、内反肘変形、橈骨神経麻痺、正中神経麻痺などが挙げられます
骨折の程度によって分類され
重症度が変わってきます
Gartlandの分類
・Type1:転位が全くないか、ごく軽度のもの
・Type2:折れ曲がっているが、一部の骨皮質に連続性が残っているもの
・Type3:完全に転位してしまっているもの
いずれにしても、顆上骨折はしっかり治さないと合併症の可能性が高いものなので注意が必要です
肘頭とは、肘を曲げたときに一番出っ張るところ
肘の頂点のことをいいます
肘頭は二の腕と前腕とをつなぐ蝶番(ちょうつがい)の役目を担っており、肘関節の曲げ伸ばしをなめらかにする働きがあります。
肘頭を骨折すると、上腕の後ろにある上腕三頭筋に引っ張られ、肘頭が破断し、折れた骨の欠片が引き裂かれた状態になります。
骨折の原因は肘をついて転倒などによる直達外力によるものと
上腕三頭筋の牽引力によって起こる介達外力によるものとに分かれます
症状としては、ひじを自由に動かすことができず、肘頭は二の腕と前腕とをつなぐ蝶番としての役目を果たせなくなります。
また、ひじのあたりが著しく腫れて、押さえると激痛を感じるようになります。場合によっては、ひじのあたりを触るとくぼみがあり骨が折れているのがわかることもあります。
また、骨折の仕方にもよりますが、上腕三頭筋の腱がついていることによって、骨片が後上方へ転位することがあります。
この場合は、自分でひじを動かすことがむずかしくなります。
さらに、単純な骨折だけでなく
肘関節の靱帯損傷肘関節の靱帯損傷やモンテギア骨折、鉤状突起骨折などの合併症を伴うことも少なくありません。
骨折の応急処置は
1、Rest:安静
2、Icing:冷やす
3、Compression:圧迫
4、Elevasion:挙上(患部をなるべく心臓より高く上げること)
以上の4点が重要となってきます。
ただし、一般の方が「圧迫」を行う場合には「軽く圧迫する程度」に留めておいて下さい。
これは、末端に血液がいかなくなるほど強く圧迫してしまうと血流障害を引き起こしてしまうことがあるからです。
また、骨折した部位が動かないように副子(添え木)で固定してあげることも大切です。
ダンボールや箸、板など何を使っても構わないので、骨折した患部にあてがい包帯などで留めましょう。
腕の骨折が疑われる場合は、三角巾を使用するのもよいでしょう。
膝の側副靱帯は関節の側方動揺性を安定させる機能があります
膝の側副靱帯には、内側側副靱帯と外側側副靱帯の2つあります
内側側副靱帯は膝関節の内側、大腿骨(太ももの骨)から脛骨(内スネの骨)についており
足が固定された状態で外側から強い力がかかり
膝が内側へ入ると靱帯が引っ張られ、その力に耐えられなくなって損傷します
逆に外側側副靱帯は膝関節の外側、大腿骨から腓骨(外スネの骨)についており
足が固定された状態で内側から強い力がかかると損傷します
側副靱帯は膝が捻れることによっても引っ張られてしまうので、足が固定されたまま膝で振り向くような動作でも損傷することがあります
損傷の程度はⅠ度〜Ⅲ度に分類されており
Ⅰ度が軽度の損傷でⅢ度が重症になります
・Ⅰ度は靱帯の繊維の微小損傷で損傷範囲も狭く、関節の不安定性もみられません
・Ⅱ度は靱帯が部分的に断裂した状態で軽〜中等度、関節の不安定性がみられます
・Ⅲ度は靱帯が完全に断裂し、関節の不安定性も大きくみられます
場合によっては骨折を伴う可能性もあるくらい重症となります
内側側副靱帯は前十字靭帯、内側半月板と同時に損傷すると【不幸の三兆候】といわれ、スポーツ選手にとって致命的な状態となるので注意が必要です
半月板とは大腿骨(太ももの骨)と脛骨(スネの骨)で構成されている膝関節の間にある軟骨様の板のこと
C形をした内側半月板とO形をした外側半月板があります
半月板の役割は
膝関節にかかる衝撃の吸収
関節の適合性
滑液の分散などがあげられます
この半月板が損傷し、炎症を起こしてしまうと、膝の運動時に痛みやひっかかり感、膝周囲の腫れ、熱感がでてきます
その状態で放っておくと、関節内に水が溜まってしまうことがあるので早急な処置が必要となってきます
損傷しやすい過程として、膝に体重がかかった状態で関節を捻る
例えば、バスケットのような急発進・急停止時
ラグビーのように足を地面に固定された状態でタックルを受けると損傷しやすくなります
膝の前十字靭帯、内側側副靱帯と3つ同時に損傷したものを不幸の三兆候といいスポーツ選手にとって致命的なものとなります
少しでも痛みや違和感などの症状を感じるようであれば早めに受診をした方がいいです
肩関節にある腱板が炎症または断裂を起こした状態のこと
若い年代では野球などの投球動作によって起こることがあります
「腱板」という言葉自体は耳にしたことがある方が多いと思いますが
「結局腱板ってなに?」と思われる方もおられるでしょう
腱板とは
肩関節にある棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋の4つの筋肉を合わせて腱板と呼びます
正式には【回旋筋腱板】や【ローテーター・カフ】といい、いわゆる肩関節のインナーマッスルのことです
腱板は肩関節を動かすときのメインの筋肉ではなく補助をする筋肉ですが
この筋肉が上手く働くか働かないかで肩関節の運動の効率が違ってきます
特に野球などの投球動作のように肩関節を捻った動きをする場合には重要となり
野球選手が行っているチューブトレーニングではこれらの筋肉をメインに鍛えています
腱板を損傷し、治療によって痛みや炎症が治ったら
トレーニングや投球フォームを改善することにより、再発を防止していくことも可能です
当院では治療だけでなく、フォームの改善も行なっているので
気になる方は体を痛めていても、痛める前でも一度ご相談ください
カカトが痛いときは疑ってもいいかもしれません
足の指の付け根からカカトまで膜のように張っている筋肉・腱の組織に炎症が起こったもので【足底筋膜炎】や【足底腱膜炎】と呼ばれます
多くは足の裏、カカトの骨の前の方に痛みがでますが、足の指の付け根や土踏まずに痛みがでることもあります
足の裏は縦アーチ(足を横から見たときにあ弓状に湾曲している)と横アーチ(足を前から見たときに弓状に湾曲)と呼ばれる湾曲があり
縦アーチは土踏まずを形成しています
そして足底筋膜がこの縦アーチをつくっています
このアーチは歩く、走る、ジャンプの着地時にバネのように衝撃を緩和させる役割をしています
使い過ぎによる筋肉の過緊張
筋力の衰えによるアーチの低下
扁平足
立ち仕事が多い
などによって負担がかかると足底筋膜炎を起こしやすくなります
この疾患も炎症を起こしている時期はアイシングが重要になってきています
当院にはスポーツを休めない患者さんがたくさん来られます
そんな患者さんには、足底筋膜炎専用のテーピングを貼ってスポーツを続けてもらいながら治療をしていきます
その名の通り、アキレス腱に炎症が起こって痛み・腫れ・熱感や足を曲げにくくなった状態
アキレス腱とはふくらはぎの筋肉の延長で足のカカトにつきます
それによって普段通りに歩いたり、走ったり、ジャンプしたり、つま先足立ちをしたりすることが可能となります

スポーツなどの激しい運動により、ふくらはぎの筋肉が緊張してしまうとアキレス腱に負担がかかり炎症を起こしてしまいます
アキレス腱炎になりやすい要因として
・ふくらはぎの筋肉に繰り返し負担がかかる
・ウォーミングアップをせずに、急に激しい運動を始める
・ハイヒールを履くことが多い
・足に合わないシューズを履く
などが挙げられます
これらに当てはまる方は注意が必要です
この疾患は悪化するとアキレス腱を断裂してしまう可能性があるので
早めの処置、治療が重要になってきます
初期や痛みが強い場合はアイシングや超音波治療などによる物理療法
ある程度痛みがとれてくると、運動療法やストレッチでの原因となる筋肉の柔軟性の確保・筋力アップをして再発を防止します
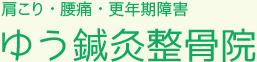
〒559-0022
大阪市住之江区緑木1-1-2
田中ビル1F
住之江区北加賀屋駅3番出口より徒歩3分
スーパーダイエーさん向かい
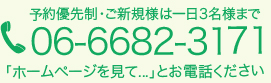
| 受付時間 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 9:00〜12:00 |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯
(8:30〜13:00) |
| 15:00〜20:00 |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
- |
※日曜・祝日・水・土曜午後は休診です。
※お名前とご希望時間をお伺いしてご予約が完了します。