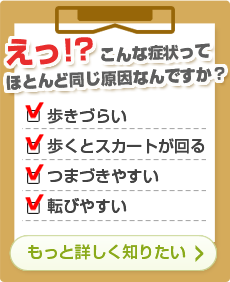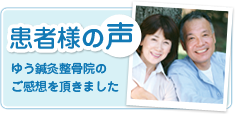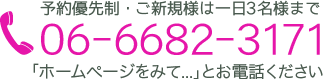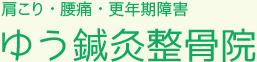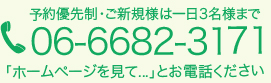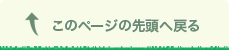新着情報
「若い人はもっと魚を食べなさい」。
若いうちは魚よりも肉を好んで食べがちです。家に帰って魚が出てくるとテンションが下がるという話も聞いたことがあるくらいです。
でも「魚ならどんな魚でも食べまくればいい」かというと、そういうワケでもありません。
動脈硬化を引き起こす原因の1つとされる鉛、水銀、カドミウムやヒ素などの有害重金属。
マグロなどの大型魚にはそれらが蓄積している可能性があります。
例えば、火力発電所の煤煙。これには水銀が含まれていて、空気中に放出されます。
雨が降ると一緒に海水に混ざり、それがプランクトンの体内へ。
それを小魚が食べ、その小魚を大型魚が食べ…と、水銀がどんどん濃縮されていきます。
ちなみにアメリカ人よりも魚文化がある日本人は、体内の水銀濃度が約5倍多いそうです。
魚を食べる際はマグロなどの大型魚をばくばく食べるよりも、日本近海で採れるサンマ・アジ・イワシなどの青魚の方がいいかもしれません。
青魚にはDHAやEPAが豊富に含まれているのでオススメです。
ゆう鍼灸整骨院のホームページはこちら
引用元:食べすぎて良い・悪い魚
いきなり汚い話ですが、焼肉を食べた次の日の便って臭いがキツくないですか?
これ、キムチと合わせて食べると抑えれることがあります。
理由はキムチには消化酵素だけでなく乳酸菌も含まれていて、その乳酸菌が腸内の悪玉菌を退治してくれるからです。
善玉菌である乳酸菌は腸内環境を整え、健康や老化予防だけでなく、美容にも重要になってきます。
腸内環の善玉菌を増やして悪玉菌を減らす
これがポイントです。
キムチの他にも納豆・みそ・ぬか漬けなど発酵食品には乳酸菌が含まれているのでオススメです。
ちなみに味噌汁は煮立たせると大事な菌が死んでしまうので気をつけてください。
腸内環境は排便ごとにリセットされるので発酵食品を毎日食べることが重要です。
ゆう鍼灸整骨院のホームページはこちら
引用元:発酵食品が悪玉菌に効く!
昔から『腹八分目がいい』と言われており、
簡単にいうと『食べ過ぎはよくない』ということです。
ではなぜ腹八分目がいいのか?食べ過ぎがよくないのか?気になったことはありませんか?
酵素には消化酵素と代謝酵素があります。
消化酵素が食べたものを消化吸収し、代謝酵素が体の細胞代謝を行い、どちらも健康な体には必要なものです。
消化酵素がちゃんと分泌されないと代謝酵素の分泌も悪くなり体に異常がでやすくなります。
食べたものを消化吸収するには「胃酸」と「消化酵素」両方が分泌される必要があります。
ある程度の年代の人がよく言う『昔はこのくらいペロリと食べたのに、最近は食べれない』
これはおそらく消化酵素が減ってきているからだと思われます。
人によって差がありますが、一生のうちに分泌できる消化酵素の量は決まっているそうです。
ということは、毎回食べまくって消化酵素を使いまくる食事の仕方をしていると
そのうち消化酵素がなくなり、食べたものを消化できなくなります。
消化不良で栄養が吸収できなくなると病気になりやすくなったり、老化が急激に進んでしまいます。
なので腹八分目で止め、消化酵素を無駄遣いしない食事を心がけましょう。
ゆう鍼灸整骨院のホームページはこちら
引用元:『腹八分目』の理由
食事のときの「食べる順番」が大切なのは紹介しましたが、それだけで終わりではありません。
次に大切なのが「食事の時間」です。
これには2つの意味があり
“一回の食事にかける時間”と
“何時に食事を摂るか”です。
今回は「食事にかける時間」についてです。
この時間はだいぶ個人差がでてくる項目で、人によっても朝・昼・夜で違ってくると思います。
ここで重要なことは『一回の食事に20分はかける』ようにしてください。
この20分は、食べ始めてから満腹中枢が刺激されはじめるまでの時間です。
20分たつまでに食べ終わってしまうと満腹中枢が刺激されず、「まだお腹が空いているからおかわり!」の状態になってしまいます。
結果余計に食べてしまい、カロリーを摂りすぎてしまい、そこに運動不足が加わるとメタボの原因となってしまいます。
この早食いを防ぐのに効果的なのがよく噛むこと。
「よく噛むと満腹中枢が刺激されて…」というのは有名な話ですが、その他にも
“血糖値の上昇が緩やかになる”
“唾液が分泌されやすくなり、消化を助ける”
“アゴの筋肉や歯茎の神経が刺激され、成長ホルモンの働きがよくなる=体脂肪が減少する”
などがあげられます。
噛む回数の目安は1口20回。
一回の食事で1500〜2000回が理想といわれています。
いきなりは難しいですが、今日から意識してよく噛んでみましょう。
ゆう鍼灸整骨院のホームページはこちら
引用元:早食い禁止
しっかり寝ているつもりでも、疲れがとれていなかったり、日中眠くて仕方なくなったり…。
そんな方はもしかしたら睡眠の質が悪いかもしれません。
睡眠時間が足りていない人は最低でも6時間眠ることを目指しましょう。
このとき注意したいのが、「夜10時からの6時間」と「夜中の1時からの6時間」では睡眠の質が全く違ってきます。
何が違うのかというと、成長ホルモンの分泌です。
成長ホルモンの有名な働きは、身長が伸びたり、筋肉量が増えたりですが
他にもたくさん身体にいい働きをしており
・代謝の促進
・血糖値を一定に保つ
・恒常性の維持
・エネルギー不足の状態の時、脂肪組織からエネルギーをつくる
などがあります。
また、アンチエイジングにも効果があるとされ、成長ホルモンを投与する研究も行われたそうです。
しかし、外部から投与すると発がんなど様々な副作用の可能性が指摘されたそうで安易には行えないそうです。
やはり、体内で自然に分泌される成長ホルモンが重要ということになってきます。
この成長ホルモンがもっとも分泌される時間帯が夜の22時〜2時の4時間といわれており、その時間に睡眠していることが重要です。
大人になって仕事をしていると、22時に布団に入るのは難しいかもしれませんが、「せめて23時に布団に入る」「毎日が無理なら3日に1回」など、まずは『できるときだけ』からでもはじめてみてください。
成長ホルモンの分泌が悪くなると病気になりやすくなるのでご注意を…。
ゆう鍼灸整骨院のホームページはこちら
引用元:いい睡眠と悪い睡眠の違い
居酒屋など飲み屋に行ったときに出てくる「お通し」や「つきだし」。
お店に寄って出てくる物は違いますが、酢の物が出てくることが多くあります。
少し前に話題になり、今ではほとんど常識となっている「食べる順番」。
この食べる順番はすごく大事です。
例えば同じ定食を食べるにしても、順番によって消化や吸収・代謝の過程が大きく違ってきます。
定食がテーブルにきて、いきなり白ご飯をかき込むと血糖値が急上昇してしまいます。
血糖値が急上昇すると、その後反対に急降下してしまいます。すると、下がって血糖値を早く上げたくなるので甘いものが欲しくなる悪循環に陥ってしまうことがあります。
急上昇、急降下をして血糖値が上下すると、イライラしやすくなるので要注意です。
話は戻りますが、「お通し」で酢の物が多いの理由ははじめに酢の物を食べると身体にいいからです。
どう身体にいいのかというと…
①胃酸の分泌が促進される
②消化吸収がよくなる
③血糖値の急上昇を抑えれる
この3つの理由からです。
結果、ご飯を美味しく健康的に食べることができます。
もし酢の物がない場合はおひたしなどの野菜から食べます。
煮物類は砂糖を使っていることが多いので後回し。
まず野菜→魚や肉類→ご飯を少しずつ食べてから
あとは好きなように食べてもオッケーです。
ゆう鍼灸整骨院のホームページはこちら
引用元:お通しに酢の物が多いのはなぜか
古くから漢方としても使われるスイカ。
果肉の赤い部分にはリコピンやβカロテンが含まれており、抗酸化作用が期待できます。
白い皮の部分に多く含まれているカリウムやアミノ酸の一種のシトルリンには利尿作用があり、体内の毒素を出したり、むくみの解消に役立ちます。
また、エネルギー補給にぴったりです。
皮の白い部分は、漬物や炒め物にするのがオススメです。
最近ではさまざまな種類のブランドスイカが出ているので、食べ比べてみるのもいいですね。
ただし、食べ過ぎには注意しましょう。
ゆう鍼灸整骨院のホームページはこちら
引用元:スイカを食べて夏バテ予防
夏は暑さで熱中症などが心配になり、外で運動できる時間は限られてしまいます。
しかし、家でも運動ができるとしたら
時間やタイミングを気にせずに済むので嬉しいですね。
暑いとついダラダラしてしまいがちですが、簡単なトレーニングで夏の運動不足を解消しましょう。
まずはトレーニングの準備です。
“ウォーキングで体を温める”
①肩甲骨を動かすことを意識し、腕を大きく振りながらその場で足踏みをします。
②このとき、膝は腰の高さまで直角になるように上げます。
これを1分程度でいいのでトレーニングの前に行ってください。
次にトレーニングです。
“体の後ろ側を鍛える”
①仰向けに寝た状態からお尻を軽く浮かせます。
②お尻、腰、背中と浮かせ、膝から肩が一直線になるように意識します。
③肩甲骨と肩で床を押すようにし、背骨と胸を押し上げて約20秒静止。
平気ならこれを3セット行います。
最後に
“腰痛予防のストレッチ”
①仰向けになって、両腕でふくらはぎを抱え込む。
②ふくらはぎを抱える両腕に少し力を入れ、胸と太ももの空間を埋めるように引きつける
③足首あたりで両手を組むと効果がアップします。
これも1分くらい行います。
はじめのうちは無理のないように行ってください。
熱中症は家の中でも起こります。
適度な室温を保って運動し、水分補給も忘れずに行ってください。
ゆう鍼灸整骨院のホームページはこちら
引用元:暑い夏は自宅でトレーニング
人間の骨も新陳代謝が必要で、約3年で生まれ変わります。これは骨をつくる【骨芽細胞】と、骨を壊す【破骨細胞】
が常に働いていてつくり変えているからです。
骨の新陳代謝は30代頃までは骨をつくる働きの方が大きく、30代でつくる働きと壊す働きが同じくらいに、40代以降になると壊す働きの方が大きくなり骨量は減っていきます。
では、骨をつくる働きの方が大きい成長期には骨の数はどんどん増えていくのかというと、そうではありません。
実はこの時期は骨の数が増えるどころか減っていくのです。
幼児の関節の骨は骨端(骨の端っこ)と骨幹(骨の真ん中)に分かれていて、両方の隙間には軟骨があります。
成長が止まる頃にその隙間の軟骨が骨に変わっていって骨端と骨幹がくっつきます。
このため幼児の骨の数は約305個ですが、大人になると200〜206個に減っていくのです。
成長するのに骨が減っていくのは不思議ですね。
引用元:成長すると骨が減る?
鼻の下に指を当ててみてください。
すると、どちらかの鼻からしか呼吸を感じられないはずです。
さほど酸素を必要としない時には、鼻の奥にある鼻甲介を1〜2時間おきに片方だけを充血させ、空気の通り道を狭くすることで片方を休ませているのです。
引用元:省エネする鼻
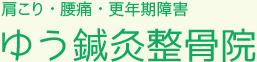
〒559-0022
大阪市住之江区緑木1-1-2
田中ビル1F
住之江区北加賀屋駅3番出口より徒歩3分
スーパーダイエーさん向かい
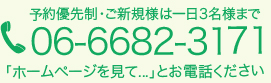
| 受付時間 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 9:00〜12:00 |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯
(8:30〜13:00) |
| 15:00〜20:00 |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
- |
※日曜・祝日・水・土曜午後は休診です。
※お名前とご希望時間をお伺いしてご予約が完了します。