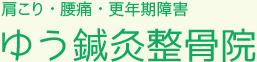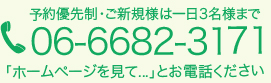新着情報
こんにちは
ゆう鍼灸整骨院です
このブログを書き始めてから、そこそこの月日が経ちました
ここでは、「当院のお知らせ」や「疾患の紹介」〜「患者さんの声」まで色んな記事を書いてきて、みなさんに読んで頂いてきましたが
記事がごちゃごちゃになって読んで頂きにくいかと思ったので
ゆう鍼灸整骨院がやっている各分野専門のブログを紹介させて頂きたいと思います
もしよければそちらも覗いてください
体を動かしやすい季節になってきました!
だからといって急な運動はケガのもとになるので
普段あまり運動をしない人はジワジワ伸ばす「静的ストレッチ」から始めるのがおすすめです
しなやかに伸び縮みするいい弾力体をつくり、筋力の衰えを防ぎましょう
ストレッチのやり方
【太ももの前側のストレッチ】
伸ばしたい方を上で横向きで寝ます
膝を曲げて、手でつま先を持ちます
手が届かない時はタオルを足首にかけて引っ張ってください
【お尻と太ももの後ろ側のストレッチ】
仰向けに寝ます
膝と股関節を曲げて、膝の後ろで手を組みます
そのまま足を胸に引き寄せます
【肩周りのストレッチ】
腕を肩の位置でまっすぐ伸ばします
反対の手でおさえてゆっくりと手前に引き寄せます
これをそれぞれ10〜30秒行います
ストレッチのタイミング
ストレッチを行う上でオススメのタイミングは
少し体を動かした後やお風呂上がりなど、体が温まっているときです
疲労回復にもつながり、お風呂上がりはリラックス効果もあります
逆にしてはいけないタイミングは
体が冷えきっているときです
寝起きなど筋肉が固まっている状態で無理に伸ばすと痛めやすくなります
ほかには食後すぐやケガなどで運動をとめられているときもタイミング的にはよくないです
ゆっくりジワジワ伸ばして「痛気持ちいい」ぐらいの加減で行ってください。
どの筋肉が伸びているか意識して行うと効果的です
おかげ様で、開業11周年を迎えることが出来ました(^^)
今後より一層、痛みや不調で悩まれている患者様に
笑顔になっていただけるよう努力してまいります!
基礎代謝とは、安静状態で1日に消費するエネルギー量のこと
年齢を重ねるとともに自然と基礎代謝は落ちていきます
例えば20代と変わらず同じ生活をしていても
40代では基礎代謝が落ちるのでエネルギーが余ります
これが脂肪となり、肥満の原因となります
肥満は健康の大敵です
骨盤底筋群とは「群」というくらいなので、たくさんの筋肉の集まり
これらの筋肉が弱くなると内臓の位置が下がり動きが悪くなります
骨盤底筋群とは骨盤の底で内臓を支える縁の下の力持ちのような筋肉群です
ストレッチのやり方
1、四つん這いの状態でそのまま上半身だけうつ伏せに。
2、左腕を右脇の下から、体に対して垂直に伸ばす。
3、できるだけ伸ばしながら、ゆっくりと息を吐き出す
4、右腕も同じように行う。
*痛くないように無理なく行ってください
1日のうちで座っている時間が長いほど心疾患などの病気のリスクが高まるという研究結果ぎあります
また、座っていると腰が圧迫されて慢性的な腰痛 にもつながるとも言われています
定期的に運動をしていても座りすぎによる健康リスクは減らないそうです
解決策として最も簡単なのは「立ち上がる」こと
デスクワークをされている方は立ちっぱなしというのは難しいので
1時間に5分くらいは背筋を伸ばすためにたちあがりましょう
3月22日(水)
●9:00~12:00 休み
●15:00~20:00 通常通り
午前のみお休みです。
よろしくお願いします。
日本では昔から梅を食べる習慣がありました。
古くは奈良時代に果物として
平安時代の日本で一番古い医学書には効用が
明治時代には伝染病の治療のために梅干しの需要が急増した
という記録があります。
梅にはピロリ菌やインフルエンザウイルスの働きを弱める「リグナン」
高血圧を抑えたり、ウイルスの増殖を抑える「ヒドロキシ桂皮酸」というポリフェノールが含まれています
また、花や実の香りの成分「ベンズアルデヒド」には抗菌作用があります
梅干しには健康効果がありますが、10gに1gの割合で塩分が含まれており、食べ過ぎると塩分の摂り過ぎになります
食べる場合は1日に2個を目安に。
ちなみに、、、、
自家製の梅酒を作っている方は
誰かにふるまう目的で作ると酒税法違反になるそうです
また、アルコール分20%以上で漬けなければ違法になるのでご注意ください
たとえば足首を捻挫したとき
日にちが経てば勝手に治る!
運動するけど、いちいちテーピングは面倒だから今日はなしで!
とケガを甘く見ていませんか?
少しの打撲くらいならそれでも問題ないかもしれませんが、捻挫や骨折となると話は変わってきます
足首の捻挫は靭帯が部分的または完全に切れている状態です
靭帯が大なり小なり切れているのに、それをほったらかしてしまうと治りが遅くなったり、キレイに引っ付かないまま痛みがなくなって治ったと思い込んでしまいます
部分的に切れている靭帯を固定せずそのまま運動してしまうと、完全に切れることもありますし痛みがどんどん増えてしまいます
また、キレイに引っ付かずに治ってしまうとその部分が通常よりも弱くなってしまい再発しやすくなります
運動を休んで固定するのが一番ですが、う
冬場は寒さで体が縮こまって硬くなりがち
さらに暖房器具のある部屋でじっとしていることが多くなります
そんな状態でいきなりウォーキングや散歩をすると心配になるのが転倒です
普段と同じようなつもりでも足が十分に上がっておらず、小さな段差でつまづいてしまうかもしれません
お尻〜ふくらはぎにかけて伸ばすことが少ないので、お出かけ前に軽くほぐしておきましょう
猫のポーズ
背中、腰、お尻、太ももの後ろが伸びます
①四つん這いになり、首や肩の力を抜きます
②手は動かさず、お尻を後ろに突き出します
猫が伸びをしているポーズになります
ふくらはぎのストレッチ
①壁に手を当て、片足を後ろへ
②かかとを床につけたまま、もう片方の脚を曲げながら前にすり出します
この2つを自然な呼吸、痛みのない範囲で20〜30秒キープします
お出かけ前に少しストレッチするだけで転倒の確率が下がるなら安いものです
ケガをしてからだと、痛いうえに治るまで時間もかかってしまうので試してみてください
寒さも厳しくなり、体が冷えると筋肉が硬くなります
筋肉が硬くなると血行が悪くなり、これが体の痛みの原因になることも
筋肉の緊張を和らげ、血行を良くするストレッチで固まった体をリラックスさせましょう
血行が良くなると肌荒れやくすみも改善されます
肩周り、腰の筋肉を緩めます
①あお向けに寝て右ひざを立てて、左手で右ひざを持ち、息を吐きながら左足の上に倒します
②右腕は真横に伸ばすか、ひじを曲げて肩が楽に感じる位置に。そのまま5〜6回呼吸します。
③反対側も同様に行います
肩の柔軟性をだします
①両足を組んであぐらで座り、息を吸いながら、右腕を背中に向かって曲げる。
②息を吐きながら、左手を下から後ろに回し、両手をつないだままで5〜6回呼吸。届かなければタオルを用いてもOK
③反対側も同様に行います
ポイント
・体を温めてから行うこと
・腹式呼吸でゆっくりと呼吸し、吐くことを意識する
・反動や弾みをつけず、ゆっくりと「気持ちいい」と感じる程度で行う
このポイントを意識しながらカチコチになった体をほぐして血行をよくしましょう
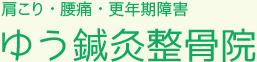
〒559-0022
大阪市住之江区緑木1-1-2
田中ビル1F
住之江区北加賀屋駅3番出口より徒歩3分
スーパーダイエーさん向かい
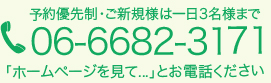
| 受付時間 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 9:00〜12:00 |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯
(8:30〜13:00) |
| 15:00〜20:00 |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
- |
※日曜・祝日・水・土曜午後は休診です。
※お名前とご希望時間をお伺いしてご予約が完了します。